著者:自由人銀次

土佐久礼小学校に通う1年生・矢吹健一は学校が終わると同学年の釣り好き仲良しグループを誘って地元桂浜ビーチで泳いだり釣りをして遊ぶことが日課になっていた。そんなある日、砂浜で遊び疲れて休んでいた健一達の後ろで、謎の老人から声を掛けられる。なんと彼の正体は、世界中を旅する伝説の釣り師「銀次」。彼は、健一達に伝説の海神「ドングー」を釣りたいと熱い思いを語る。健一達は、その熱い思いを聞いて、果てしない冒険の一歩へと踏み出すのであった。舞台は南紀白浜、釧路など全国に広がり、子供たちはそれぞれ釣りにかかわりながら成長していきます。はたして、ドングーと遭遇できるのか……スペクタクル冒険ファンタジー。そして衝撃のクライマックス!
第1章 伝説の釣り師「銀次」との出会い ~高知桂浜編~
——- 「ザザーン」 ——- 静かな波が繰り返し防波堤に打ち寄せる ——
その時子供達は、防波堤の海側に設置されたテトラポットの上で、網を持ってグレの稚魚を狙っていた。


防波堤の上でその様子を見ていた八千代は、建一のすくった小魚が桜鯛の子供だと確認すると残念そうに言った。・・・そう、この辺りでは桜鯛の稚魚が多く住んでいて、すぐに餌取りされる場所である。
——- ここは高知県土佐市桂浜の海岸べりに建てられた防波堤の上 ——-
子供達は地元の土佐久礼小学校に通う一年生の仲良しグループである。建一はグループのリーダー格で、活発でいつも元気いっぱいの男の子。少しおっちょこちょいだが、トレードマークの赤いヨットパーカーが良く似合う。
智は建一と同じクラスの一年生だが、背は建一よりも10センチも低く、女姉妹に囲まれているせいか草食系のキュートな感じの男の子であった。いつも建一に連れ添っていて、同学年なのに弟みたいな存在である。

八千代は隣クラスの頭の良いしっかり屋さん。眼鏡を掛けているが勉強はずば抜けており、クラスでも一番の秀才であった。

建一はタコ獲りの名人だが、料理でタコを捌くのは下手で、食べるのはもっと苦手であった。

八千代の友達の花子はこの近くに住む漁師の娘で、今居るテトラポットのすぐ脇の道路沿いに花子の家があった。

八千代は携帯電話で花子にそう伝えると、防波堤の端まで移動して智に言った。

智はいつもお姉ちゃんと一緒に家の料理の手伝いをするので、小さいながら料理は得意であった。将来の夢は大好きな日本食の料理人になりたいと思っている。
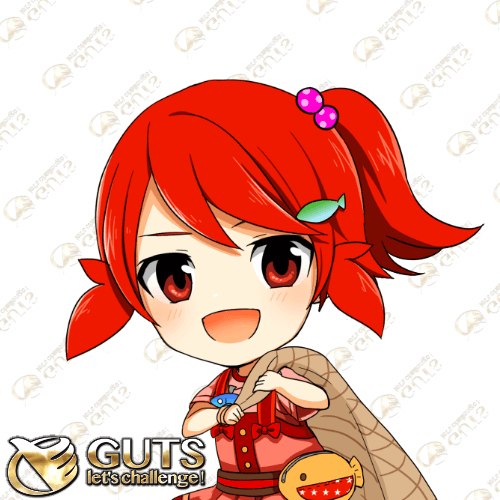
花子がタコ用の疑似餌を持って、堤防の上を走って来た。

智がいつもかぶっている緑の帽子を取って手を振ると、花子は息を切らせて智に走り寄り、持って来たタコ獲り用の小さなサバの姿をした疑似餌を手渡した。

智がそう言うと、ノリの良い建一は明るく鼻歌調に返した。

お調子者の建一はノリが良くていつも軽い口調で冗談を言うが、あまり受けたことがない。

青い太縁の眼鏡を右手で上にずらしてそう言うと、いつも冷静な八千代は少し眉をひそめた。八千代の両親は久礼で大学と高校の教師をしている。
かたや花子は幼い頃から髪の毛にポイントで赤色のメッシュを入れている。漁師一家に育ったせいか、曲がったことが大嫌いな気の強い女の子であったが、持ち前の明るさでクラスでは人気者であった。
土佐は南国高知の中でも指折りの漁師町で、人口のおよそ半分は漁業関係の従事者で構成されている。土地柄であろうか、今でも人情にあふれた古き良き日本の近所付き合いの風情が感じられる、カツオがメッカの田舎町であった。
ここに住む漁師達は一本釣船に乗ってカツオを追い、一年のうち半分以上は外洋に出て漁をする。
子供達も皆この土佐で生まれて、気が付けばいつの間にか海を遊び場に育っていた。
建一はテトラポットの上から疑似餌の付いた糸を垂らして、慣れた手付きで上手に竿を誘導してタコを誘った。この辺りではタコ以外にもたまにカレイが掛かったりして、釣り人を喜ばせたりする。テトラポットの下側は砂浜になっており、数は少ないがワタリ蟹も生息していたので、思わぬ獲物が掛かったりすることがあるのだ。
智と八千代の期待を受けて、建一はタコに挑戦し続けたが、この日は調子が悪かった。

建一があきらめた様子でそう言うと、智が残念そうに言った。

この辺りの子供達の趣味と言えば、大体がゲームと海釣りであった。仲の良い子供達が何人かで「土佐久礼小チーム」として仲良しグループを作っていた。建一達のグループも男女合わせて十人程度の仲良しグループになっていたが、それぞれが個性の違う子供達が集まって、その中には外国人の子供も混じっていた。土佐南高校で英語教師をしている両親を持つ、ジョニィとマリーの双子である。
面倒見の良い建一は、クラスに編入してきたジョニィとすぐに友達になっていた。また、隣のクラスだが同じ仲良しグループのみどりも、ポジティブなマリーの行動力に惹かれて大の仲良しになっており、明日はチーム皆でタコ釣りに挑戦して、智の家で料理をして食べようということになった。

——- 翌朝、子供達は桂浜ビーチに集まり、投げ釣りをしていた。 ——-

達也はそう言って竿を大きく振ると、スカイブルーのマイキャップをかぶり直して気合を込めた。この辺りはゴカイの投げ釣りで五目釣りが楽しめるのだ。

クラス委員長をしている達也は、グループ一の理屈屋でもあった。眼鏡を掛けて一見ひ弱そうに見えるが、勉強だけでなくスポーツも得意で、父親は土佐タクシーの社長をしていた。地元でも名士の子供である。

建一が達也にそう言うと、達也は一番長い投げ釣り用の竿をジョニィに手渡した。

しかしアメリカ人のジョニィは子供ながらに力が強く、遠くに投げようと貸してもらった竿を力一杯に振ってしまって、釣り糸が途中でプツンと切れてしまった。

智は釣りの初心者のジョニィに投げ方のコツを優しく教えるが、いつも強気のジョニィは言うことを聞かない。

ジョニィは糸が切れたのを道具のせいにして言い返した。
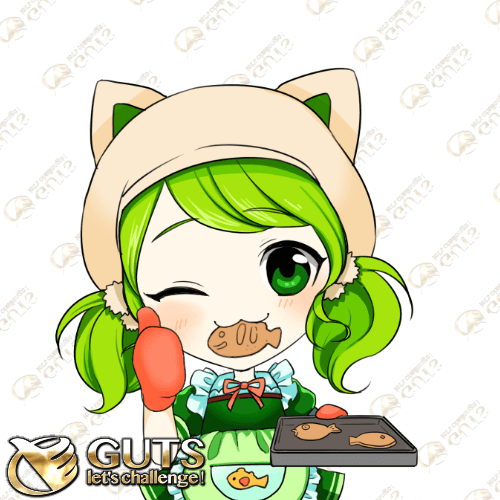
二人のやり取りを聞いていたみどりが、間に割って入ってそう言った。
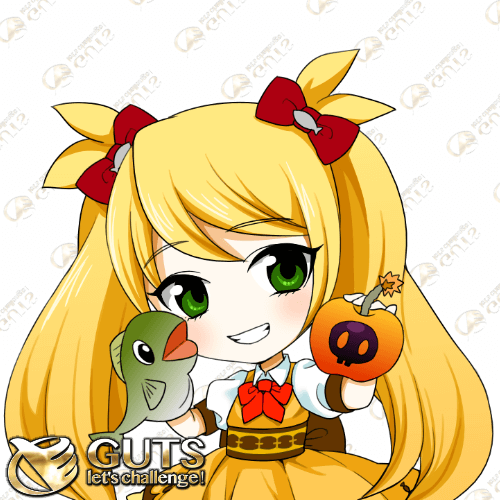
ジョニィと双子の兄妹のマリーは正義感が強く、日本に来て早く友達と仲良くなろうと努力している。自分勝手なジョニィに諭すようにそう言った。二人共綺麗な金髪である。・・・するとその時突然大きな声が響いた。

大きな声の主はグループで一番の腕白坊主の翔であった。翔の竿先が少し前のめりにしなって、確かに何かが喰いついているようだ。翔は真っ黒なジャージを砂浜に脱ぎ捨て、必死で素早くリールを巻き上げた。
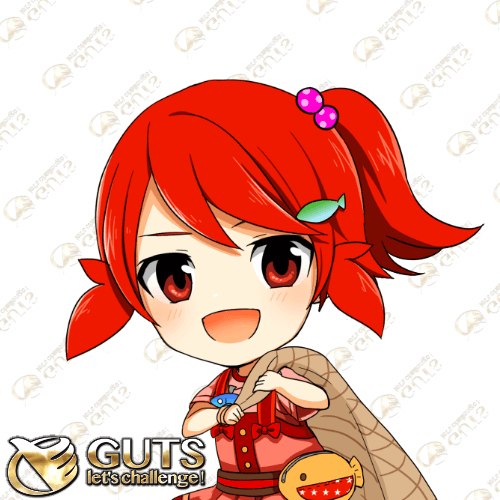
波打ち際に上がってきた獲物を確認して、花子が嬉しそうに言った。

翔は初めて釣れたタコを見て、少し興奮気味に叫んだ。

タコ獲り名人の建一がそう言うと、八千代がすぐさま返すように話した。

物知りの八千代がドヤ顔で説明する。じゃあタコの属性は朝方と言う事か。
確かに海釣りで重要なことは、その生物の生態や属性に合わせて竿は勿論の事、釣り糸やリール、重りや釣り針などの道具を使いこなすことで、自分の持つスキルや釣り技がより一層生きてくることである。まだテクニックのない八千代ではあったが、海釣りの知識だけは正しかった。
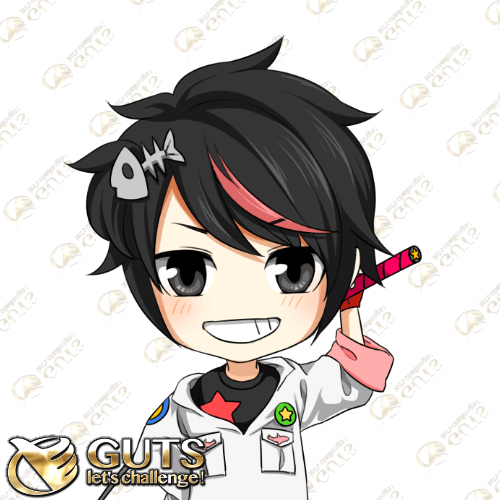
わがままな洋子が突然、吐き捨てるように言った。洋子は黒髪の綺麗な、ちょっとヤンキー的美少女である。釣りのゲームは得意だが、実際の海釣りは初めての経験であった。朝から投げ釣りに挑戦しているが、なかなか当たりがこなくてイラついていた。
お父さんは洋子の幼い頃に亡くなっていて、お母さんが久礼の村で一軒しかないパン屋を一人で営んでいる。
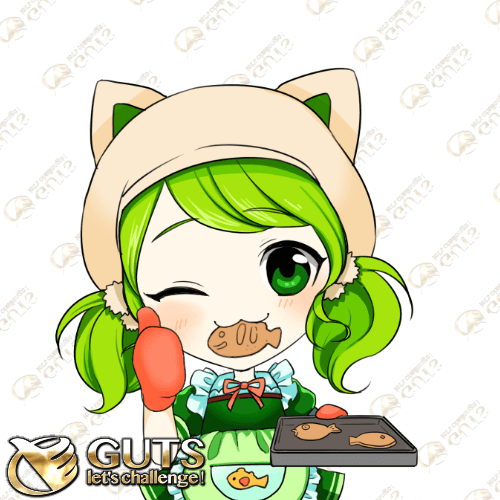
みどりは天然のブリッ子だが、いつも頑張り屋さんでもある。明るいキャラクターで、皆の癒し係として認められていた。トレードマークは緑のスカーフである。

元気な建一の掛け声で、皆がそれぞれ一斉に竿を投げた。初夏の久礼では今の時期は魚影が濃くて、子供達の腕でもキスやカレイなど、さまざまな魚を釣り上げることができた。
また桂浜の海岸は遠浅で、子供達の絶好の海水浴場でもあった。この日も投げ釣りに飽きた時には、皆で下着だけになって、目の前の青い海原で目一杯泳いで遊んだ。
子供達は元気だ。お昼に洋子が家から持って来た菓子パンを食べたあとも、投げ釣りでたくさんの獲物をとり続け、波打ち際で泳いだり砂浜を駆け巡って遊んだ。
・・・その時、時刻はもう夕方の六時になっていた。日中は熱く砂浜を照らしていた太陽も気が付けば西に傾き、岬の灯台の上に差し掛かろうとしていた。
——- 折しもその時、砂浜で遊び疲れてたむろして座っていた子供達の後ろに、謎の老人「銀次」が一人静かに佇んでいたのであった。 ——-

突然の銀次の問い掛けに、子供達は少し驚いて振り向いて応えた。

智は後ろにいた銀次の顔をのぞき込んで答えた。

銀次は子供達が朝から投げ釣りを楽しんでいたのを、防波堤の上で見ていたようである。
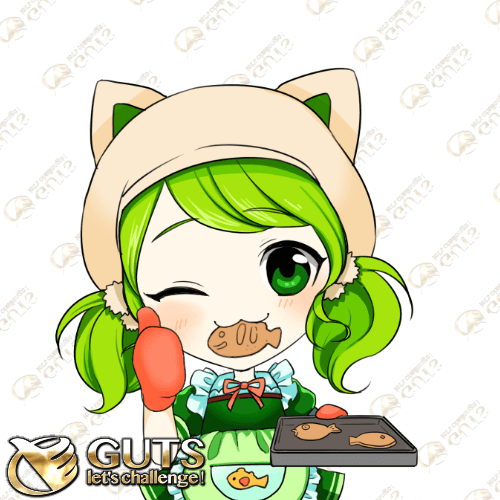
皆初めて見た人なので、みどりが聞いてみた。

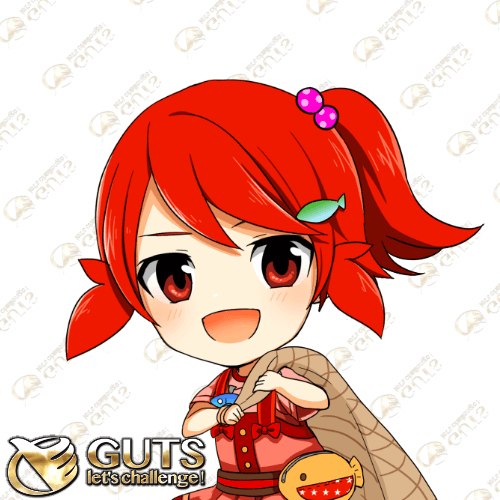
花子は不思議そうに聞いた。

皆が岬の先を振り返ると、確かに一艘の白いクルーザーが泊まっている。船の横に船名が書かれていて、遠くではっきりとは確認できないがよく目を凝らして見ると、どうも横文字の金色で「GUTS号」と書いてあるようだ。

子供達はこの老人が世界中の海を駆け巡って暮らしていると聞いて驚いた。年の頃は六十歳を超えているように見える。この時リーダー格で活発な建一が怪訝そうに銀次に尋ねた。

子供達は皆一斉に銀次の顔をのぞき込んだ。


銀次はゆっくりとしゃべり出すと、静かに一度目を閉じて何かを思い出すように大きく目を見開いた。

銀次は心の中に溜まったものを吐き出すように突然口を開いた。

建一達は初めて聞くその名前に不思議がって、銀次に聞き直した。

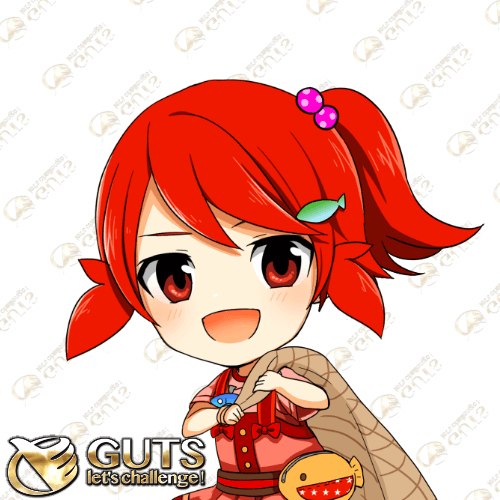
花子は少し怖そうに眉をひそめた。

銀次はそう言うと、子供達の横に腰を下ろした。

銀次はそう言うと、腰に挟んでいたキセルを咥えて火を点けた。

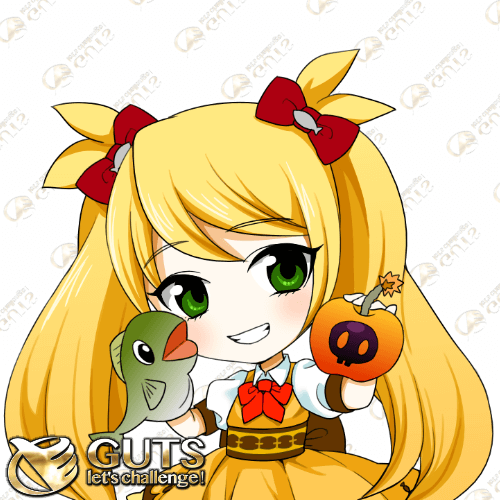
マリーが言った。英語教師をしているマリーの父親は、家で地球儀を使ってよく外国の話をしてくれる。

子供達は銀次の話に聞き入りながら、恐る恐るお互いの目を見つめ合った。

ごくっ・・・子供達は唾を飲み込んで、もう一度銀次の顔をのぞき込んだ。すると銀次はふっと優しそうな眼差しで、子供達の顔を見つめて続けたのであった。

銀次は話しながら、その目にうっすらと涙を浮かべているようであった。・・・伝説の海神ドングーに対する銀次の熱い思いが、幼い子供達にも十分に伝わっていた。

八千代と花子は、ほぼ同時に同じ事を聞いてみた。

そこまで話すと銀次は、何かを思い込んだようにその細い目に力を込めて大きく見開いた。

智の心が躍った。

銀次は両手を大きく広げて、それを包み込むような仕草をして話した。

建一がそう言うと、子供達は大きく頷きながら一斉に立ち上がろうとした。

銀次が子供達をなだめるように静かに言うと、子供達は怪訝そうな顔をしてお互いの顔を見つめ合った。

子供達の純朴な問い掛けに、銀次は困ったように少し首を傾けて話を続けた。

銀次は子供達に優しく諭すように説明したが、一度火の点いた子供達のハートは熱く燃え上がり、収まりそうもなかった。

達也の言ったこの言葉を聞いた銀次は、再び目を閉じて座った両ひざの前に手を組んだ。そして首を下に向けると砂浜をのぞき込むようにして大きくため息を一つついた。
まるで、子供達にこれから待ち受けるであろう試練を気遣い、これ以上の話を聞かせるべきかどうか、銀次も迷っているようであった。
土佐の夏は太平洋から吹き抜ける海風が頬に心地よく当たり、海岸線を抜けた海風は四国山脈を駆け上って、勢いよく瀬戸内海へと抜けていく。銀次は五分刈りだが、強い海風がその短い白髪を細かく揺らした時、思い切ったように話を続けたのであった。


それに海釣りをマスターするには腕前を磨くだけじゃなく、道具もそろえて個々の道具自体のレベルを上げなくちゃあならん。海釣りに使用する竿が特に大事なんじゃが、それ以外にリールや釣り糸、重りに釣り針なんかもいろいろそろえるんじゃぞ。釣る時間帯や魚の種類別に合った適正な物をそろえて、その都度組み替える気配りが必要じゃ。お前達もそういった海釣りの特徴や属性を知ることから始めてはどうかのう。
初めて聞く銀次の言葉には説得力があった。

僕達頑張るよ。だっておじいさんの話を聞いて、どうしてもそのドングーに会いたくなったんだもん。・・・なぁ、皆そうだろ?
建一の発した言葉に、子供達は皆大きく頷いて首を縦に振った。
銀次の話の内容は子供達には少し難しかったが、ドングーに対して一度点いた心の火は、子供達を銀次の話す夢の冒険物語に熱中させるのに充分な迫力があった。
銀次もそんな子供達の表情を見て、うんうんと首を小刻みに縦に振りながら、更に声を大きくして話した。

じゃあ、もう少しだけ詳しく教えてやろう。いいか、いきなりドングーに会いに行くのは無理じゃぞ。まずは日々精進して自分自身のスキルアップを図りながら、様々な海釣りの経験を積むのじゃ。一口に経験と言っても簡単ではないぞ。日本中の海釣り環境の違う場所で、更に新しいチャレンジを繰り返しながら、その経験を自分の体にしみ込ませて、竿を始めとする海釣りアイテムの充実を図ることじゃ。とにかく苦しくても日々の修行が大事なんじゃよ。
銀次はそこまで話して改めて新しいキセルに火を点けると、真剣な眼差しで聞き入る子供達に言い聞かせるようにして、再び思い出すように話し出した

ここまで話すと、銀次は一度大きく深呼吸をして、キセルの煙を大きく吸い込んだ。

そう言うと銀次は砂浜から腰を上げて、右手で自分のズボンに付いた砂を振り払った。
子供達は銀次の話を聞いてまだ興奮気味であったが、銀次に諭されてめいめいが靴を履いた。
そしてその場を去る時には全員が、その心の中にドングー伝説にまつわる銀次の言葉を沁み込ませていた。
「ミャー・・・ミャー・・・」海猫達も海岸での散歩を終えて、山の方角にあるであろう自分達の巣へと群れを成して帰って行く。

名残惜しそうに銀次に背を向けて去って行く子供達の小さな背中に向けて、銀次はその姿が見えなくなるまで小さく手を振って見送った。

銀次の見つめる目の先は、もう夕日が岬の灯台に隠れて、長い久礼の一日が終わろうとしていた。
試し読みでは、ここまでとなります。この続きは、製品版でお楽しみください。












